【山田醸造】味噌蔵の新しい挑戦
- NIIGATA CITY OCTAGON TOURISM

- 2024年12月6日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年1月9日
新潟青陵大学 村山ゼミとともに、未来へ向けた新潟市の魅力創造・発信を目指すプロジェクト「未来創造学生会議」
今回、そのメンバーで訪れたのは、山田醸造株式会社(新潟市北区葛塚3119)。
明治24年創業、歴史の深い味噌蔵で、蔵見学のナビゲートをしてくださったのは、6代目 山田弥一郎さん。
味噌蔵ならではの視点で、味噌づくりの工程や発酵に係る新しい取組みなどをレクチャーいただきました。

趣のあるお店や醸造現場を舞台に、山田さんは「味噌がどうできるのか」「発酵がもたらす変化」などを、映像資料を駆使しながら丁寧に分かりやすく説明してくださいました。
実際に、こういった蔵見学や発酵のリテラシー向上への取組みは、外国人の方たちにもニーズは高く、蔵を訪れる機会も多くあるそうです。
さらに、山田醸造の取組みは味噌づくりだけに留まらず、発酵の力を活用した社会課題の解決にも挑戦しています。
その中でも、新潟県の厳選野菜をモチーフに、野菜を発酵させることでスープのベースにもなる新商品「Bread Dip Cozy(ブレッド ディップ コージー)」などの開発を通した、蔵元として目指す未来への姿をお聞きしました。
ー 新しく開発した商品とは?
トマトをベースにした、野菜本来の味が感じられる“コンソメのようなスープの素”です。
山田屋は、「発酵に挑戦し、学び、進化し続けます。」をモットーに、明治24年から発酵食品を製造しています。この商品は、その発酵技術を活かして、新たな食材に挑戦しました。
通常の味噌の原材料は大豆と米と食塩ですが、この商品は野菜を素材とし、化学調味料や保存料は一切使用せず、野菜の素材本来の味を、発酵を通じて引き出しました。その結果、優しい野菜の風味にすっきりとした味わいの美味しい野菜スープの素が完成しました。
お客様に新しい味わいを提供できることを楽しみにしています。
ー 開発のきっかけは?
商品開発のきっかけは、特別な菌でつくった米糀でした。この米糀を活かして、新しい発酵食品を創りたいという思いから、試行錯誤が始まりました。
最初は、醤油麹や塩麹のような試作品を作成し、ドレッシングにも挑戦しましたが、なかなか満足のいく結果になりませんでした。そこで、「美味しいものを作ろう」という原点に立ち返り、再度試行錯誤を重ねました。
その過程で、私たちは様々な食材や調味料を試していると、味噌やディップソースのように使い切れずに冷蔵庫に残っていることに気付きました。この「もったいない」気持ちは、お客様にも共感されることだろうと思い、使い切りのスープの素を開発する方向に舵を切りました。
特に、毎日の忙しい仕事に追われながらも健康を大切にする女性の方々に、「野菜×発酵」の力で元気になってもらいたいという思いが強く、それを手軽に自宅で楽しんでいただける商品を目指しました。

ー 難しい挑戦ではなかったですか?
商品開発に際して、いくつかの課題に直面しました。
まず、開発を担当した職人が以前は調理師としての経験がありました。その経験を活かして、それぞれの野菜がどのような味わいになるかは、予想が立てやすかったです。しかし、味噌では使わない野菜を具体的にどう使って、どのような組み合わせでにするのか。また、何を足したり引いたりして最適な味わいを追求するのかが、一番苦労したポイントでした。

また、野菜本来の味を感じられるように、最適な塩分量を探し出すことも必要でした。
さらに、野菜の品種や生産者によって味や色合い、香りが異なることに気付きました。同じトマトでも生産者や季節、品種による違いがあり、無限の組み合わせを考えるのが難しかったです。
そのため、生産者の方に訪問し、コミュニケーションを取ることがとても重要で、この過程が私にとって楽しい日々でした。

ー 蔵元の目から地域の野菜を見るというのは、すごく新鮮ですね
はい、そうですね!また、B級品やC級品といった品質が低いと見なされる野菜を積極的に使い、発酵の力で美味しい製品に仕上げたいと考えました。ただし、これらの野菜は通常よりも洗ったり皮をむいたりする作業に時間がかかります。しかし、これらの野菜を使用することで、生産者の方が一生懸命育てた野菜を無駄にしないよう頑張っています。
ー 山田屋(山田醸造株式会社)のこと?
山田屋は、明治24年(1891年)創業の蔵元です。この年は、初代 弥惣治の醤油業が軌道に乗った記念すべき年でした。 元々、織物事業に取り組んだもののうまくいかず、町外れだった葛塚(旧豊栄)に蔵を構えて再チャレンジしたのがスタートでした。
3代目 久一は、新潟県内の仲間である同業者同士の競争を嫌い、関東圏への販路拡大を目指しました。大きな詐欺にあい倒産の危機に直面しましたが、盗まれた味噌が関東大手問屋の口に入り「この味噌は美味しい」と、関東圏での販路拡大への足掛かりになりました。
現在、6代目弥一郎は、創業から受け継いだ技術と想いを大切にしつつ、新たな発酵食品の開発に挑戦しています。山田屋は味噌や醤油の発酵調味料の技術を活かし、現代に合った新しい商品を模索しています。
地元のお客様だけでなく、ネット通販を通じて県外や海外にも発酵技術を提供し、若い世代に魅力的な産業を提供することに取り組んでいます。山田屋は歴史と伝統を尊重しながらも、常に進化と挑戦を続ける企業です。

ー 未来創造学生会議(学生)に期待することは?
若い人たちがこれから次の子供たちを育てていきますので、そういう方たちに(発酵の魅力を)広めてもらう、知ってもらうというのは一番意味があることなのかなと思います。











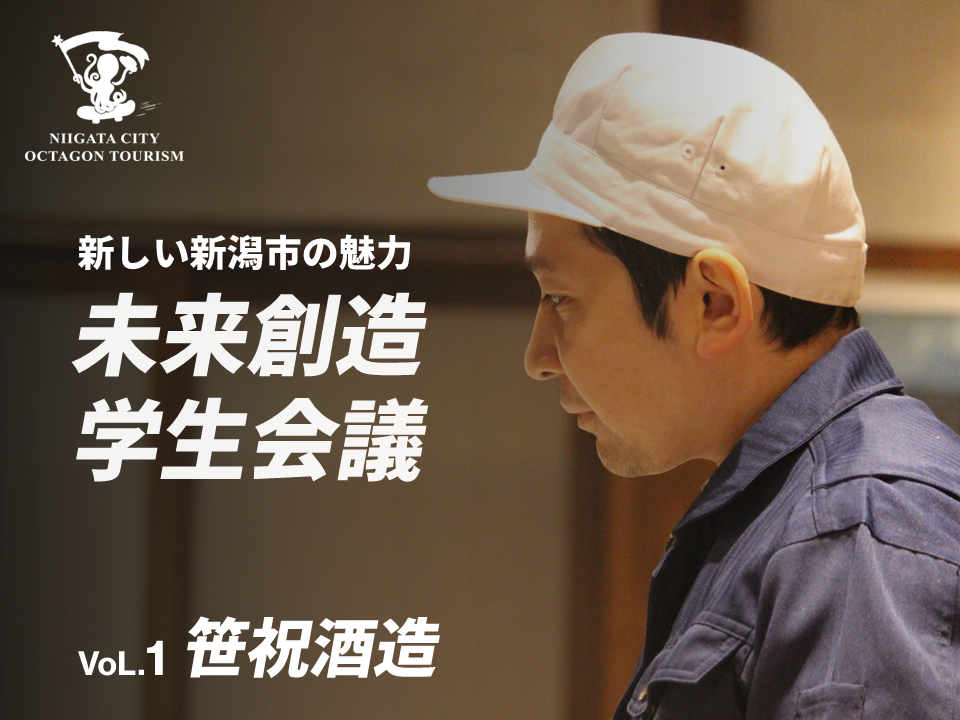
コメント